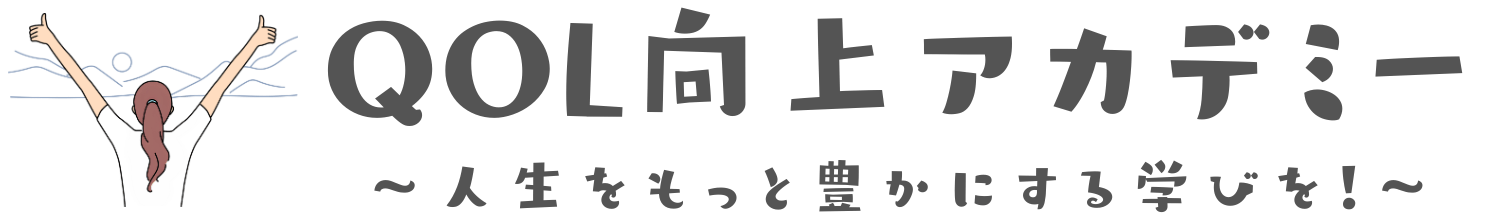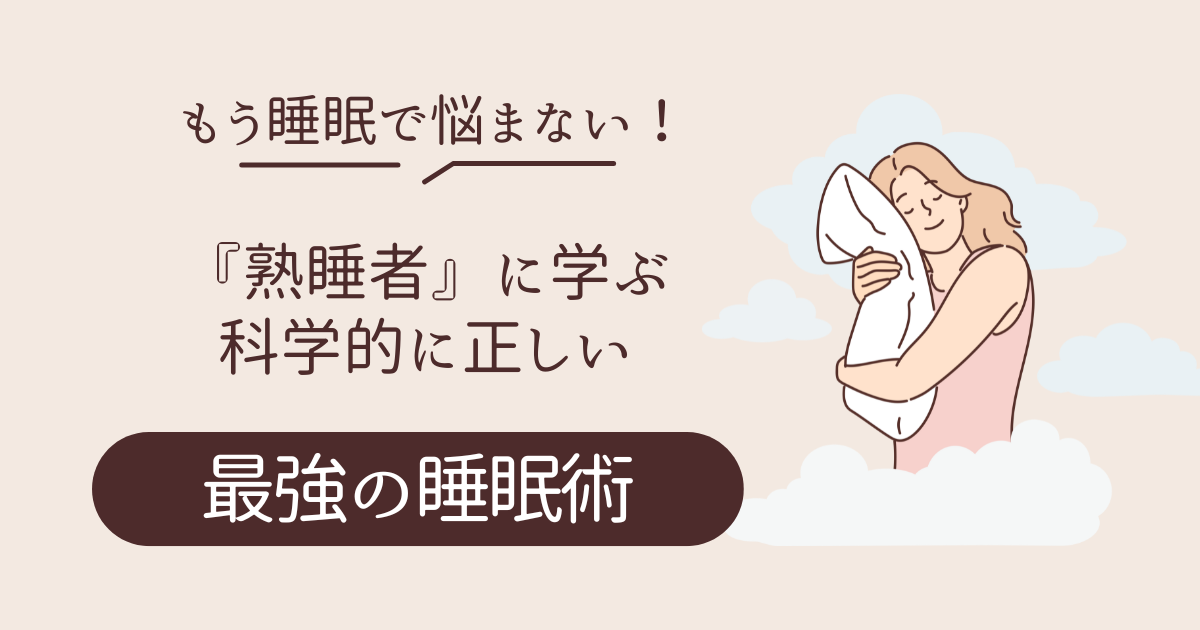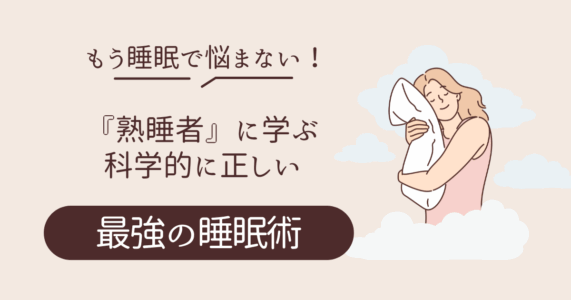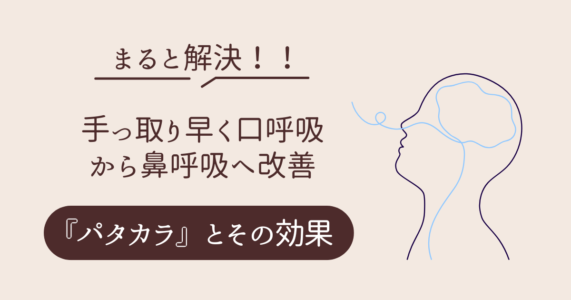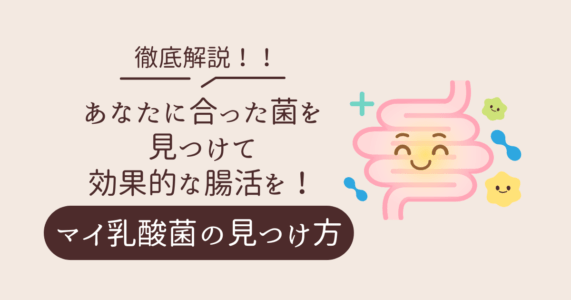今回は”睡眠の質を改善したい方“、”睡眠の悩みを持つ方“におすすめしたい本『熟睡者』について紹介します。
また私自身この本を読んで、自分自身にも取り入れたいことをまとめましたので、併せて紹介したいと思います。
 管理人
管理人正直、睡眠に関しての悩みはこの本1冊を読めば、ほとんど解決されるんじゃないかと思うくらい、有益な情報がたくさんありました。
私自身不眠症のため、睡眠に関する知識はかなり深いです。
その私からしても、最新の睡眠に関する情報や、これまで私が仕入れた知識も網羅されていました。
この本に書いてある情報は、科学的根拠に基づいたデータや実験の結果を通じて、効果を説明してくれているので、『なぜあなたが眠れないのか』、『なぜ眠りの質が悪いのか』、など様々な観点から原因を説明してくれています。
また、睡眠の仕組みや、睡眠の意外な効果も説明してくれています。
『SNSが睡眠に与える影響』『睡眠による記憶の定着と学習について』『睡眠が与える心の安定とストレスや不安の解消などの効果』『精神的なバランスを維持する役割』『睡眠不足による体重増加・肥満のリスク』『睡眠が美容・外見に与える影響』『睡眠がもたらす免疫力や糖尿病との関係』『睡眠時無呼吸症候群について』など
この本を読んだことによって、いかに睡眠が多方面に影響していて大事なのかが分かりました。
睡眠に関して悩んでいる方は、まずはこの本から手にとっていただいてもいいのではないかと思っています。
【大前提】睡眠は「起きている時間にしたこと」で決まる
この本を読んで一番大事な考えだと感じたことは「睡眠は起きている時間にしたことで決まる」ということ。
例えば、朝のうちに外へ出て日光を浴びて、明るいうちに運動し、夕食は少量にとどめ、夜はスマホやPCを遠ざけるなどをしたらどうですか?
ほとんどの人が睡眠は改善し、夜ぐっすりと眠れるようになるのではないですかね。
つまり「睡眠とは、丸一日24時間の行動の産物ということ」なんですよね。
だからこそ、覚醒時の行動には気をつけたほうがいいんです。
睡眠を改善したいと思うなら、睡眠にプラスに働く習慣を身につけていく必要があるんです。
続いて、ボクがこの本を読んで取り入れたことを『朝編』『昼編』『夜編』『運動編』『食事編』『寝る前編』などに分けて、この本に書いていることを一部抜粋して紹介したいと思います。
【朝編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
朝、日光を浴びる
朝のうちに太陽の光をたっぷり浴びた人は、その夜に質の高い睡眠を享受できることが、研究でも明らかになっています。
そして心身ともによい1日のスタートを切るには、他のどの光よりも、太陽の光が適しています。
こちらの本によると、晴れている日なら、屋外に「30分」もいれば十分。
曇天だと太陽光線が弱いため、同量の光を浴びるには「約1時間」、外で過ごす必要があるようです。



正直、30分も外にいられる時間はないという方もいるかもしれませんが、自分のできる範囲で太陽を浴びる習慣をつければいいのかなと個人的には思います。
また、日中、外出する機会のない人は、窓のそばに座るようにしたほうがいいとも書いています。
もし太陽の光を浴びることが難しいなら、「昼光色ランプ」を設置して問題を解決することができるようです。
自分のできるやり方で工夫して取り入れてみてください。
「朝コーヒー」の効果
朝、コーヒーやお茶などカフェイン入りの飲み物を摂取すると、体内時計のスイッチが入る効果があると考えられています。
朝のコーヒー1杯に含まれるカフェインが全身の代謝に非常に重要な役割を果たす肝臓の1日のリズムを整えるのに役立つからです。
なので朝一番に1杯ないし2杯のコーヒーを飲むことは睡眠の観点からも、やはりいいようです。
ただ、午後の遅い時間にコーヒーなどカフェインが含まれるものを飲むと、間もなく日が暮れ、夜も近いということを体が理解できず、心身ともに長く冴えた状態になってしまうので注意が必要です。
飲む時間によってコーヒーは敵にも味方にもなりうるということですね。
【昼編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
人間の体は「1日2回」眠る設計
昼食後の眠気について話していこうと思います。
昼食後の眠気は、食べたものを消化するために疲労感を覚えると考えている人が多いようですが、眠気が生じるのは消化のためだけではありません。
私たちの体内時計には昼食後の休息がプログラムされていて、午後13時〜15時の間に短い睡眠をとることは極めて自然なことだといいます。
昼寝は睡眠・覚醒リズムのごく自然な構成要素で、「私たちの体は本来、1日2回睡眠をとるまうに設計されていて、連続して7~9時間眠るようにはできていない」と考える研究者も多いとのことです。
昼寝は「15分以内」ならプラスになる



夜の睡眠不足を補うには昼寝が役立ちますが、あくまでも短時間にとどめることに気をつけてください。
脳の前頭葉に息抜きの時間を与える上でも、昼寝はした方がいいとのことですが、15分を超えないのが条件。
そうしないと、夜の深い眠りの時間が減少するデメリットが生じるとのこと。
ホルモン分泌の観点から、夜の深い睡眠のほうが昼寝よりも高い疲労回復と再生効果をもっているからです。
長い昼寝にともない夜の睡眠の質が低下し、再生のプロセスが十分に遂行されないので昼寝の時間は十分に気をつけてください。
【夜編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
手足が温まって「睡眠に合った体温」になる
就寝前に熱いシャワーを浴びたり、バスタブに浸かったりして体温を上昇させることは、睡眠をうながす効果があり、早く眠りにつくための自然な方法です。



就寝直前の手足の皮膚温度の上昇は、脳にとって「体温を下げ、眠りの準備を始める時間がきた」という合図になるので、ぜひ意識してみてください。
【食事編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
食事は「7〜19時」の間にすませる
健康的な食生活をすることが体によいということは、ほとんどの人が理解していると思いますが、「食事のタイミング」も私たちの体に大きな影響を与えます。
規則正しい時間に食事をとることが、体内時計のリズムを整え、いつ眠り、いつ覚醒すべきかを体に知らせる上で役立っていることが、研究で証明されています。
つまり、食事の時間を体内の腹時計に合わせることで、睡眠・覚醒リズムによい影響を与えることができるということです。
遅い時間に重めの食事をたくさんとると、翌日に備えて休息をとろうとしていた腸は夜勤シフトで働くことを余儀なくされます。
また、空腹でないにもかかわらず食事をとると、体内時計に混乱をもたらします。
そして研究結果によると、『7時~19時の間に、規則正しく食事をとる人』は、気が向いたときに食べる人よりも、よく眠れることが立証されています。



仕事の関係で、どうしても夕食の時間が遅くなってしまう方もいるかもしれませんが、なるべく19時までの間に食事を済ませるようにできると、睡眠の質が上がるようですので、早めの食事を心がけてみてはいかがでしょうか。
「食べたもの」で眠りが変わる
肉類や脂っこい食べ物
「玉ねぎ」は腸でガスを発生、睡眠の邪魔に深夜勤務やそのほかの理由によって、
肉類や脂っこい食べ物は胃の中に長くとどまるため、体は遅くまで働きつづけ、長く起きることを強いられます。
また、玉ねぎや食物繊維を多く摂取する人も、睡眠が妨げられる可能性があります。
これらの食材は腸内にガスを発生させ、腸の夜間の休息が奪われることになりますので、仕事の関係でどうしても夜遅くに食事をとらなければならない人は、せめて食事のバランスに注意しましょう。
バターやチーズの「飽和脂肪酸」は入眠を妨げる
バター、赤身肉、チーズなどに含まれる「飽和脂肪酸」の過剰摂取は人眠を妨げ、睡眠が断片化する調査結果もあります。
それに対し、魚類や豆類、ナッツ類に含まれる「不飽和脂肪酸」は比較的消化されやすいです。
「牛乳」でスムーズな入眠に
なかなか寝つけないときに「ホットミルク」が良いと聞いたことはないですか?
これはけっして根拠がないわけではなく、牛乳に含まれる「トリプトファン」といラアミノ酸が、睡眠ホルモンであるメラトニンの生成をうながすため、入眠しやすくなります。
そのため、コップ1杯の牛乳は、実際に入眠に役立つ効果があります。
入眠効果のある果物「サワーチェリー」
メラトニンを多く含み、睡眠導入効果をもつ果物もあるがあります。
それが、「サワーチェリー(酸味の強いサクランボ)」です。
研究によれば、果汁のほうが、新鮮なチェリーよりもメラトニンの濃度が高いといます。
もし入眠に問題があるが牛乳が好きでない、もしくはアレルギーがあるという人は、就寝前にサワーチェリーのジュースを試してみてはいかがでしょうか。
【運動編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
「運動」する時間で朝型になったり夜型になったりする
運動は健康に良いだけでなく、睡眠・覚醒リズムを安定させ、質のよい睡眠をもたらす効果があります。
しかし、運動する時間に関しては注意が必要です。
外が明るいと、「体内時計が体をフル稼働させ、栄養を調達する時間だ!」と指令を出します。
外が暗くなり、寝る時間が近づくと、体は徐々に省エネモードに入り、体温を下げて、脳と体中の器官に「回復しなければならない、眠る時間だ!」という指令を出します。
そのため睡眠・覚醒リズムの最適化を図るには、午前中に運動する方が良いです。



午前中運動することによって、太陽光をたっぷり浴びることができ、夜の適切な時間に睡眠欲を高められるんです。
また、7~8時の間、もしくは15~17時の間に持久系のスポーツをすると、光の有無に関係なく、体内時計が朝型へ調整されることを示す新たな研究もあるようです。
逆に、19~22時の間にランニングをすると、体内時計が後ろにずれてしまうとの研究結果も出ています。
そのため、発汗がうながされるような運動は、遅くとも就寝3~4時間前には終わらせる方が良いでしょう。
【寝る前編】睡眠の質を上げるために取り入れたこと
「寝室」の温度を下げてぐっすり
室温と質のよい睡眠の間には関連があることが、研究でも確認されています。
就裏前の室内温度を上げすぎないように注意!
多くの人は冬に寝室を20度にまで暖める方も多いかもしれません。
しかし、最適な睡眠のためには、これでは暖かすぎます。
寝室の暖房は、就寝前に弱めたほうがよいでしょう。



寝室の温度は涼しめに保つこと、夏はクーラーをつけ、冬は暖房をきつくしすぎないようにすることが大切です。
体温の低下は、体のすべての細胞にある体内時計に、夜が始まって眠りの準備を開始する時間がきたことを知らせる合図ともなるのです。
「酸素」がたくさんあった方がよく眠れる
夜の間は十分な酸素量を確保することも睡眠にはとても大事です。
複数の研究で、窓を開けたままの方がよく眠れるという結果が出ています。
寝室のドアを閉じずにおくだけでも、空気の循環が著しく改善されることが分かっているようです。
スクリーンと紙で「読後の眠り」が変わる
PCやスマホの画面から発せられるブルーライトは太陽の光に似ているため、体内のメラトニン分泌が遅れ、それにともない睡眠の時間が後ろにずれてしまうことが分かっています。
それにより入眠時間は遅くなり、夜に眠気を感じにくくなり、レム睡眠の時間が短くなり、起床時の疲労感が増加したという実験結果も出ています。



ただしこれには続きがあります。
日中に十分な光を浴びていた場合は、輝度を最大に設定したタブレットを2時間使用しても、睡眠に影響を与えないという結果が得られたんです。
このことから、太陽の光の下でアウトドア活動やスポーツなどを行うことで、画面から発せられるブルーライトによる睡眠障害は予防できる可能性があるのです。
つまり、スマホなどから受けるブルーライトの影響の大きさは、日中にどのくらい光を浴びたかに左右されるということ!
したがって、ブルーライトばかりが悪者になっているが、太陽の光が不足していることが問題の根底にあるんです。
ということで対策方法について
睡眠研究者の多くが、少なくともベッドに入る2時間前には、画面のある機器のスイッチを切ることを推奨しています。
さすがにそれは難しい方も多いと思いますので、
- 夜の間だけでも、ブルーライトカットめがねをかける
- 液晶端末の設定でブルーライト画面の色温度を調整(iPhoneのナイトシフト、Androidのナイトモード、PC用のフリーソフトf.luxなど)
- 朝どうしても太陽の光を浴びられない人は、午前中に昼光色ランプを使う
ToDoリストを作成すると入眠しやすくなる
ある研究では、翌日にやらなくてはならないことをToDoリストにメモしておくと、入眠時間が短くなると言う結果が出ています。
次の日の全体像を把握することで、体内のストレスが軽減されるのではと考えられています。



頭の中がスッキリして、ごちゃごちゃと頭の中の考えがなくなるので、これはオススメですよ!
本当に「眠れない時」の最終手段
とは言いつつ、いろんな睡眠法を試しても、結局眠れないということは誰しもありますよね。



それもそのはず!「寝れない!」「睡眠が足りない!』と焦るほど、体はコルチゾールを多く分泌し、眠りにつくのがますます難しくなるんです。なので⬇︎
①どうしても寝れないときは、そのまま静かに横になって過ごす
暗闇の中に横たわっていれば、脳は外部の大方の情報から遮断され、ゆっくり休めます。
最適でなくとも、ある程度の休息をとることはできるはずです。
そして、満足に眠れなかったとしても、朝起きた時には、太陽の光を目で浴びて、しっかりと朝食をとり、今後に備えて体内時計と睡眠・覚醒リズムを整えることが何よりも大事です。
②また、例え眠れなくてもポジティブにとらえることが大事
「20分しか眠れなかった」ではなく、「20分も眠れた」というように。ひとつずつクリアしていくことが大事です。



これは私の話ですが、どうしても寝れないときは、「もういいや!今日は寝ない!」と逆に起きてようとしています。



もちろんその時でもスマホはいじらず、横になって目を瞑りながら、「寝ない!」と起きてようとするんです。



そうすると気づいたら寝ている日もあるので、やはり眠ろうと眠ろうと焦るのが一番良くないと思っています。
まとめ
『熟睡者』を読んで、体内時計を「自分」で調節するためにボクが取り入れたこと・取り入れたいと思ったことを下記に簡単にまとめました。
- 外に出て、日光を浴びる。
体内時計はとりわけ朝に敏感に光に反応するため、時間帯は早ければ早いほどいいです。
晴れた日なら30分も屋外にいれば十分ですが、曇りの日は、光の照度が弱いため外で過ごす時間を長めにとると良いです。 - 外出することができない人は、窓際に座る。
それも難しい場合は、朝のうちに太陽光に似た光を浴びられるよう、「昼光色ランプ」の導入を検討してみてください。 - 夕方や夜間にスマホ、タブレット、PCを利用する際は、「ブルーライトフィルター」を利用する
- 運動は明るいうちに、できれば午前中にしよう。夕方から夜にかけては、体を活性化させ、入眠の妨げとなるため、激しいスポーツは避けたい。
- 寝室の温度は涼しく保つこと。
就寝前は夏であればクーラーをつけて涼しく、冬であれば暖房を弱めましょう。
寝室は酸素を入れ、空気循環にも意識してみて下さい。 - 食事はなるべく「7〜19時」の間にすませる
以上
睡眠は人生においてとても大事な要素です。ここを疎かにしてしまっては起きて行動している時間も充実した人生は歩めないと思います。
「取り入れられそうだな」「取り入れたいな」と思ったら、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。